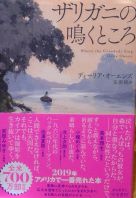真鶴
 著者 川上弘美
著者 川上弘美
文春文庫
歩いていると、ついてくるものがあった。
と始まる。
夫が、12年前に失踪した。三歳の娘を残して。女は文筆業で生活しており、今は編集者である既婚の男と恋愛関係にある。
女は、夫の日記に書かれていた真鶴に出かけていく。ついてくるもの は、女の幻覚であるらしいと、読み進むうちにわかってくる。女は、統合失調症のほうへ一歩踏み出している。ついてくる女と、会話する。幻視、幻聴。
たまたま、『死の棘』の島尾敏夫の日記が、遺族からかごしま近代文学館に寄贈された、というニュースを目にしたところであった。奥さんの島尾ミホさんが、そのために精神のバランスを崩すに至った、当時の島尾の愛人の名前が出てくるという。不都合な部分をロシア語で書いてあるという。
島尾一家の近くに住んでいたという人と、昔、話をした。後に自分でも『海辺の生と死』という優れた文章を書いたミホさんは、近くに住んでいる人から見るとやはり壊れていたということだった。
と、いうようなことを思い出しつつ、読んでいく。
恋人は、女が夫の影と今も共にあることに嫉妬の気持ちを見せる。
文筆業と言っても小説は書いていなかった女に、恋人が、小説を書くことを勧める。
夫の親が、失踪宣告申し立てをする。
そんな流れのどこかで、女は恋人と別れ、正気のところに踏みとどまる。
長い詩のようにも感じられる。書くように生まれついたひとというのは、こういうものなのだろうと、思うものがある。
三浦雅士が、解説を書いている。優れた文芸評論。私の記憶にはかつてのユリイカの編集長として染み込んでいる名前だ。