樽とタタン
 著者 中島京子
著者 中島京子
新潮文庫
今から30年以上前、3歳から12歳まで済んだ小さな町。
その町の喫茶店に、コーヒー豆が入っていた大きな樽に赤い色を塗ったものがあり、その腹には丸い大きな穴があいていた。子供の頃、保育所代わりに預けられていたその喫茶店の中に入ってじっとしていた女の子。常連の小説家が、
樽と一緒だからと、タタンと呼ぶようになった。
キャラメリーゼしたリンゴが乗っているあのケーキ、タルトタタンのもじりね。30年以上前にタルトタタンを知っていた小説家は、海外で生活していたのだろうか。
九つのお話でできているうちの、最初の“「はくい・なを」さんの一日”が、ん?なんだ?と思われるが、まあ何かしら喫茶店の扉の向こうは小さな異世界として描かれている、もしくは記憶のかなたで異世界と化している。
“ぱっと消えてピッと入る”と言う話が好きだ。明治生まれの祖母が言う。「おれは、死んだらそれっきりだと思ってる」「そのかわりによ、死んだら、ここんところへ、ぴっと入ってくんだ」と、自分の胸を指さす。マサオが死んだとき、おれにははわかった、それからずっとここんところにいるわけだ、と。
タタンと呼ばれたこの子は、言葉にうるさい。体育をたいくと言う、女王をじょうおうと、雰囲気をふいんきと、クラスメートが言うたび、ピーッと笛を吹いて黄色いカードを押し付けたいきもちになった、という、そこ。わかるわかる!そういう子供でしたよ私も。子供だからちょっとした勘違いも起こるけれどね。
子どもの頃を思い出すとき、誰にでもあるだろう懐かしい小さな世界。記憶の中でなにがしか変形し、異界に入り込んでいることは珍しくないかも。私の従姉妹の一人は、祖父母の家で兎を何匹も飼っていたように記憶しているらしいが、鶏は飼っていたよ、兎?一匹ならずたくさん?私の記憶にも別の従弟の記憶にもそれは存在しない。
この子供は、小説家の予言通り、小説を書く大人になっている。小説や詩を書かないタイプ、ストーリーがきちんとあるものが好きなタイプには、あまり向かないかもしれない。お話です。あなたはどう感じた?




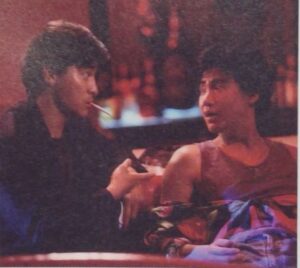

















そうでしたか。酒へのこだわりとか、別に軽口たたいてるわけじゃないけど読み手になに…