
「リバー」
奥田 英朗/2022年
発行:集英社
同一犯か? 模倣犯か?
群馬県桐生市と栃木県足利市を流れる渡良瀬川の河川敷で相次いで女性の死体が発見!十年前の未解決連続殺人事件と酷似した手口が、街を凍らせていく。かつて容疑をかけられた男。取り調べを担当した元刑事。娘を殺され、執念深く犯人捜しを続ける父親。若手新聞記者。一風変わった犯罪心理学者。新たな容疑者たち。十年分の苦悩と悔恨は、真実を暴き出せるのか───
人間の業と情を抉る無上の群像劇×緊迫感溢れる圧巻の犯罪小説!
Amazon商品ページより
2024年5月現在、奥田英朗の長編ミステリーの最新作。
ネットで中古品を購入。
届いた本を手にして驚いた。こんなに分厚いとは! 想定していなかった。
しっかり自立してるし、ずしっと重い。
読み応えありそうだと心が躍るものの、しかしこれではベッドに横になって読むという通常の読書スタイルが取れない。ちょっとした待ち時間にバッグから取り出すには、ちょっとばかり大げさ過ぎる。なぜ上下巻に分冊してくれなかったのか。大好きな作家さんなのに少々恨みがましい気持ちにもなる。
ネット情報によると、単行本一冊の平均ページは一般文芸書でだいたい300ページ前後だそうだ。本書は648ページ。分冊しても良さそうだが、それでも分けずに売られているのには何かしら訳があるのだろう。
例えば上下巻にすると上巻だけ売れるというのが出版業界の”あるある”だという。
私も「銃・病原菌・鉄」の(上)だけ読んで、(下)は手付かずのまま本棚にある。学術的な要素のあるノンフィクションだと、上巻だけ読んで投げ出してしまう堪え性の無い人も多いだろう。
エンタテインメント系の小説の場合だと、序盤ゆっくりと物語が進み中盤以降から盛り上がってくるスタイルも多く、そういうタイプは分冊し難い。
あるいは分厚くても一気に読ませる力量のある作品なら、あえて分けないこともあるかもと想像したりする。
実際に「リバー」を読み始めると、ページをめくる手が止まらない。
「分厚くても一気に読ませるぜ!」という出版社の気概を感じる。
本の厚みは登場人物の多さを物語っている。
桐生南警察署の捜査員たち、足利北警察署の捜査員たち、事件記者、退職した元刑事、被害者遺族、犯罪心理学の大学准教授、複数の容疑者、容疑者に関わる周辺の人々。
多種多様な人たちが登場する。登場場面が少ない人でもモブキャラ扱いはしない。周囲に迷惑かける人、かけられている人。変わり者。問題を抱えた人たち。登場人物を描く作者の眼差しは暖かい。そこが奥田英朗の作品の魅力だと、私は思う。
そしてなんといっても、くすっと笑っちゃう場面がそこかしこにある。
シリアスな犯罪小説であっても、なんというか、日常の中にある人間の可笑し味を表現するのが上手い作家だなあと思う。
どんなに分厚い本でも最後のページはやってくる。体力的に一気読みはできず、二日目に読み終わった。
結末については、登場したかれらの話をもっと聞きたいと思う気持ちが残った。例えば3年後の話でもいい。あれから彼らはどうなったのだろうと。そう思わせて終わるのだから、むしろこれがいい結末だったと思う。
読み終わってからAmazonのレビューに目を通してみたら、私同様、本の厚さに驚いている読者がいて、ちょっと笑ってしまった。
ひょっとしたら、本を分冊していないのは読者を驚かすためだったのか?
追記
今回登場した犯罪心理学の大学准教授・篠田は「トンデモ精神科医・伊良部一郎」を思い起こさせる変人ぶりだが、伊良部よりはマイルドな感じ。
いずれ「犯罪心理学の大学准教授・篠田」を主人公とした物語も生まれそうな気がする。
生まれて欲しいな。

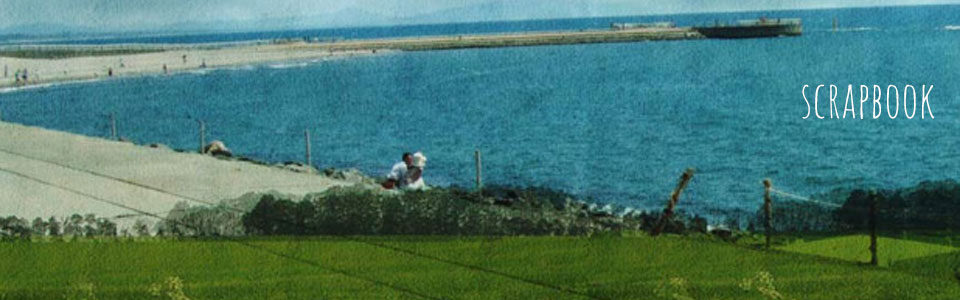
 2024年7月13日
2024年7月13日 











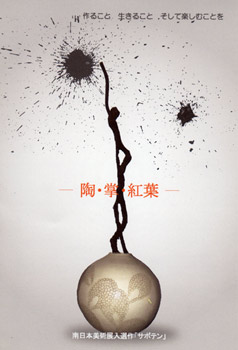





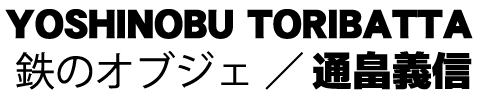



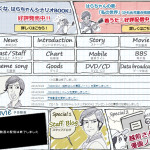













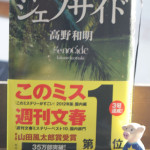
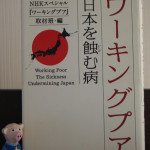

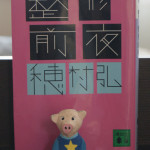
 LINEのプライバシー設定完璧ですか?納得の解説動画みつけました
LINEのプライバシー設定完璧ですか?納得の解説動画みつけました 「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」観てきました
「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」観てきました 6/16日から「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」
6/16日から「2024宮崎国際現代彫刻展・空港展」 pcで落としたスマホを探す(アンドロイドの場合)
pcで落としたスマホを探す(アンドロイドの場合) 「リバー/奥田英朗」分厚くても一気読みしたいミステリー
「リバー/奥田英朗」分厚くても一気読みしたいミステリー ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き
ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き 「100人展in薩摩川内」のご案内
「100人展in薩摩川内」のご案内 「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ
「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ 『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』
『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』