同時通訳者の頭の中って、一体どうなっているんだろう?異文化の摩擦点である同時通訳の現場は緊張に次ぐ緊張の連続。思わぬ事態が出来する。いかにピンチを切り抜け、とっさの機転をきかせるか。日本のロシア語通訳では史上最強と謳われる著者が、失敗談、珍談・奇談を交えつつ同時通訳の内幕を初公開!「通訳」を徹底的に分析し、言語そのものの本質にも迫る、爆笑の大研究。
(Amazon.co.jp「BOOK」データベースより)
どこかで名前を聞いたことがある、という程度に知っている著者だったので、『不実な美女か貞淑な醜女か』という怪しげなタイトルと表紙イラスト故、別のジャンルの本と誤解して手を出さずにいました。
最近、偶々目にした読書ブログで「文句無く面白い」と紹介されていて読んでみる気になったのですが、ホント、文句無く面白かったです。
米原万理さんはロシア語の同時通訳者として活躍され、「テレビの同時通訳により正確で迅速な報道に貢献したとして日本女性放送者懇談会賞」を受けた方だそうです。
本書は、「働く女性」のエッセイであるばかりでなく、その実態をあまり知られていない同時通訳者達のドキュメントでもあり、示唆に富んだ国際論、異文化論でもあり、爆笑間違いなしの小話満載、お笑い本でもあり、といったところ。
含蓄のあるメッセージが多く、私の目からもウロコが何枚か剥げ落ちました。
例えば、私などは自分が英会話ができないことを棚にあげ、いやだからこそというか、各国首脳が集まる国際的場面において、我が国の総理が日本語でスピーチをしているのを見ると、「国際語をしゃべれないなんて、ちょっとかっこ悪いんじゃない?」と、恥ずかしく思ったりしたものですが、米原万理さんは、『英語で演説したがる総理大臣』に対して、どうか日本語でスピーチして欲しいと苦言を呈しています。
「言葉は、民族性と文化の担い手なのである。その民族が、その民族であるところの、個性的基盤=アイデンティティの拠り所なのである。」「どんな小さな国の人も自らの母語で、一番自由に駆使できる、一番分りやすい、一番伝えやすい、その母語で発言する権利がある」
その異文化間のコミュニケーションを取り持ち、相互理解を成立させるために、通訳や翻訳という職業があるのだ、と。
真の国際人とは、母国語で自分の言いたいことを豊かに表現出来る人のこと、という彼女の主張には説得力があります。日本人としては、まず何はさておき日本語をしっかり身につけていくことが大事なようです。ただ、私の今後の生活に外国語による会話が必要になる予定がないことは残念なのですが・・・・
米原万理さんは2006年に56歳で亡くなっています。私が読んだ2008年版の文庫では、“編集部注”として彼女の絶筆についてのエピソードが紹介されていました。そこから、最後まで真摯に、全身全霊を込めて仕事を愛し、猛スピードで人生を駆け抜けていった作者の姿が感じられ、胸を打たれます。


 2010年12月22日
2010年12月22日 

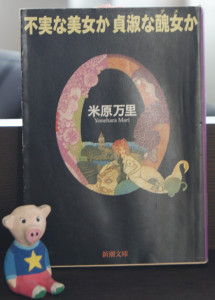




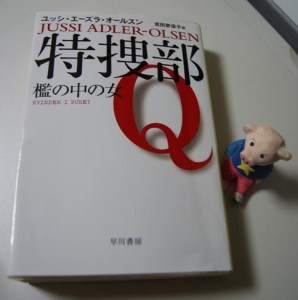






 ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き
ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き 「100人展in薩摩川内」のご案内
「100人展in薩摩川内」のご案内 「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ
「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ 『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』
『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』 睡眠研究の動画に納得!夜型人間の悲劇
睡眠研究の動画に納得!夜型人間の悲劇 10月からインボイス制度開始!おすすめのYouTube動画
10月からインボイス制度開始!おすすめのYouTube動画 二週間で読み終えられるか?図書館で借りた2冊の本ー「空白を満たしなさい」「第六ポンプ」
二週間で読み終えられるか?図書館で借りた2冊の本ー「空白を満たしなさい」「第六ポンプ」 WordPress Popular Postsに黄色の警告文が表示される【解決】
WordPress Popular Postsに黄色の警告文が表示される【解決】 「Amazon重要なお知らせ:ご注文の詳細とキャンセルについて」という詐欺メールが来ました
「Amazon重要なお知らせ:ご注文の詳細とキャンセルについて」という詐欺メールが来ました