本を読み終えて、すぐにブログに感想を書けばよいのだけど、それができずに本だけが溜まっています。あれも書きたい、これも書きたい、でも時間が経ち過ぎて記憶がどんどん薄れていく。で、今回は忘れ去らないうちに5冊まとめて、書き出してみようと思います。
 『ベイジン(上下)』
『ベイジン(上下)』
真山 仁/幻冬舎文庫
2010年4月発行
「お願いだ、俺にこの発電所を停めさせてくれ」
『ベイジン』とは北京のことで、英語ではBeijingと表記するとのこと。
舞台は、北京オリンピックを目前に控えた中国。
冒頭のセリフは、北京オリンピック開会式に合わせて運用を開始させるという原子力発電所を建設するために、中国へ招へいされた日本人技術者、田嶋の必死の叫び声です。
電源喪失、ベント操作、海水注入、といった事故場面の描写は、否が応でも福島第一原発の事故を想起させる物語ですが、作品が書かれたのは事故前の2008年。
図らずも予言の書となってしまった感があります。
「『ベイジン』は、我々がけっして忘れてはならない希望について書いた小説です。
21世紀は「諦めの時代」なのかと思ってしまうことがあります。努力しても頑張っても報われない。何かに果敢に挑むより、最初から闘わず諦めてしまう。でも諦めからは何も生まれない。
私はそう信じています。」(Amazonの商品説明、「著者からのコメント」)
 『ぐるぐるまわるすべり台』
『ぐるぐるまわるすべり台』
中村 航/文春文庫
2006年5月発行
第26回(2004年) 野間文芸新人賞受賞
「黄金らせんはオウム貝の殻や、ヤギの角などに現れることでも知られています。生物の成長というのはすなわち、相似な変形の繰り返しであるという原則が、このことからもわかります。つまり黄金比は物事が成長するときの普遍的な比率なのです。それゆえに我々は美しいと感じるのかもしれません。」
上記は、老教授が建築概論を教える講義室の一場面。こんな授業を受けてみたいものだと思いました。静かで贅沢な時間。
物語は、主人公が大学を中退するところから始まります。
彼は、塾の講師をしながら、バンドメンバー募集専用サイトでバンド仲間を探すのです。
「熱くてクール、馬鹿でクレーバー、新しいけど懐かしく、格好悪いくらいに格好いい、泣けて笑えるロックンロール。拡大と収縮、原理と応用。最高にして最低なメンバーを大募集。19歳」
彼がメンバーへの課題曲に選んだのが、ビートルズの「ヘルター・スケルター」
「ヘルター・スケルター」は、「しっちゃかめっちゃか」というような意味合いに訳されますが、元々の意味は、「らせん状のすべり台」のことだそうです。
毒気の強いニュースばかりが目につく世の中にあって、久々に毒気も悪意も一切ない青春物語を読んだなあって感じです。
主人公は、とてもナイーブ。
若い頃は私だって、いまみたいじゃない、もっともっとナイーブだったと思う。そして“若い”って昔も今も結構シンドイことだって思います。
 『火星ダーク・バラード』
『火星ダーク・バラード』
上田 早夕里/ハルキ文庫
2008年10月発行
第四回小松左京賞
「人類に進化なんてものはない。ただ、環境への過剰な適応があるだけよ。」
舞台は火星。
殺人容疑をかけられた火星治安管理局員の水島と、生まれつき他人の感情を読む能力のある少女、アデリーンとのロマンスを主軸とした、ハードボイルドタッチのSFサスペンスです。
アデリーンはプログレッシブと呼ばれる新人類。
プログレッシブは、宇宙のいかなる過酷な環境にも適応できるよう、遺伝子操作によってデザインされて生み出されるという。
「重力変化、温度変化、宇宙放射線、酸素濃度、などの異なる環境に耐え、寿命は長く、他者と不毛な争いをせず、優れた共感性を持ち、より高い知性を備えた人類」をつくるために・・・・。
人類が生き延びるには、もう宇宙に出ていくしかない未来が、いつかきっとやってくるのでしょうね。
「2023年、人類火星移住計画」によると、火星移住計画「マーズワン・プロジェクト」は、すでに現実発進しているようです。(→http://www.tel.co.jp/museum/magazine/spacedev/130422_interview02/index.html)
第1回目チームの飛行士4人を募集したところ、行ったら帰ってはこれない片道切符のミッションにもかかわらず「希望者は全世界から20万人にも及んだそうで、昨年末の12月30日、移住希望者の中から1058人の候補者が選出された。その中には日本人10人も含まれている」(「2025年、火星への片道切符の旅。日本人10人が最終選考に入る。」→http://karapaia.livedoor.biz/archives/52150116.html参照)そうです。
こんなにも勇気と犠牲精神にあふれた人たちがいるなんて、すごい!それだけでも人類の未来に希望が持てる話です。
ただ、「2023年火星移住計画“MarsOne”は夢の話だろうか」を読むと、技術的な不安要素も多く、お隣の星へ行くのも容易ではありません。
地球で死ぬも火星で死ぬも同じと言えば同じだけど、火星での開拓生活がどれほど過酷なものになるのか、想像もつかないところが怖い。
 『文章読本さん江』
『文章読本さん江』
斎藤 美奈子/ちくま文庫
2007年12月発行
第1回小林秀雄賞
「服飾史と文章史には、共通した大きな原則がある。
第一に、衣装も文章も、放っておけばかならず大衆化し、簡略化し、カジュアル化するということである。」「服だもん。必要ならば、TPOごとに着替えりゃいいのだ。で、服だもん。いつどこでどんなものを着るかは、本来、人に指図されるようなものではないのである。」
文章読本とは、「文章の上達法を説く本」のことを言う。
古くから谷崎潤一郎とか三島由紀夫とか、名だたる文豪たちが文章作法書として「文章読本」を書いてきたらしい。
本書は明治から現代にいたるまでの「文章読本」を多数取り上げ、文例をあげて(この文例が面白い!)、検証していく「文章読本」の歴史書みたいなもの。それによって文章というものが、時代とともにどのように変遷してきたかよく分かる。そして、いつもながら斎藤美奈子さんの文章は痛快!気持ちいい。
本書を読めば文章が上達する、わけでは決してないですが、小中学校の頃、作文が嫌いだった、という皆さんにぜひとも読んでいただきたい、お薦めの一冊です。
私も作文が大嫌いでした。
「嫌い」の一番の理由は、先生の「思ったことを素直に、あるがままに書きなさい」っていう言葉だったと思うのです。私の小学生の頃はそういう指導でした。
これを「作文の私小説化」と斉藤美奈子さんは言う。
まったくその通りです。
子供の頃の私には、自分の身の回りの狭い範囲のことしか題材がなく、それを書くということは、プライバシーを先生に覗かれるみたいで、すごく抵抗がありました。
大人になって、ブログというツールを手に入れた現在、書いたものをまず先生に見せる必要がないことが、とてもありがたい。
 『喪失』
『喪失』
モー・ヘイダー/ハヤカワポケットミステリーブックス
2012年12月発行
2012年度アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀長篇賞
セラピーセッションで持ち上がった問題のひとつは、コーリーがジャニスを伝統的な妻ではないと感じることがあるという点だった。
テーブルにはいつも夕食が用意され、朝はベッドまで紅茶が運ばれるにもかかわらず。
ジャニスが仕事と子育てを両立させているにもかかわらず、コーリーはなおも重箱の隅をほじくるのだ。
家に帰ったときに、焼き上がったばかりのケーキがあってほしいとか。弁当を持たせて、何なら昼食時に喜ばせてくれるちょっとしたラブレターも添えてほしいとか。
イギリスの伝統的な妻とはなんと大変なことか、と驚きました。
お弁当にラブレターを添えなくて済む分、日本の良妻賢母と呼ばれる主婦の方がまだましとさえ思えます。
ちょっと大袈裟に書いているんじゃないの?と思い「イギリスの家庭」で検索してみると、「家族に関する国際調査」(http://www.suntory.co.jp/culture-sports/jisedai/active/family/2_2.html参照)というサイトがありました。
それによると、イギリスも「急激な単身化・単親化と離婚率の上昇」があり、伝統的な家族形態は崩壊しつつあるとのこと。しかし仕事より家庭を大事にし、家族と密接な関係を持とうとする姿勢は、今も変わらないらしい。
女性の家事分担が大きいが、最近では「男性にも家事をすることが期待されていて、育児をしない男性は同性からも不謹慎にみられる」とあります。先進国と言われる国はどこも似たような状況のようです。
まあ、これは、作品の内容とはあまり関係のない話ですが。


 2014年9月14日
2014年9月14日 



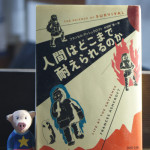
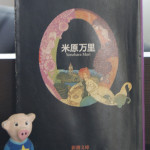
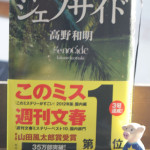
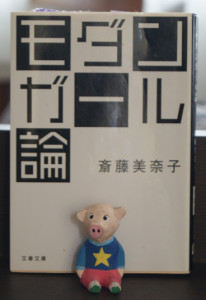


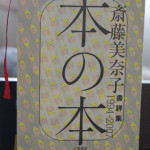








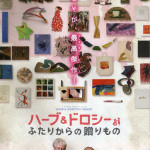
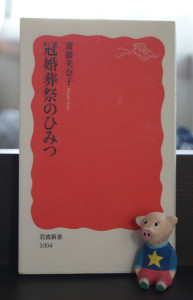

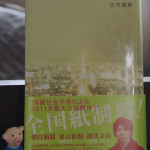


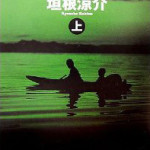
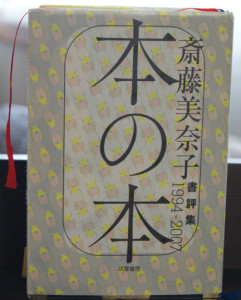

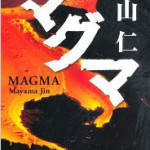



 ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き
ロリポップでデータベース5.1を8.0にバージョンアップした覚え書き 「100人展in薩摩川内」のご案内
「100人展in薩摩川内」のご案内 「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ
「2024猫展 平面と立体」開催のお知らせ 『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』
『Chatter(チャッター): 「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法/イーサン・クロス』 睡眠研究の動画に納得!夜型人間の悲劇
睡眠研究の動画に納得!夜型人間の悲劇 10月からインボイス制度開始!おすすめのYouTube動画
10月からインボイス制度開始!おすすめのYouTube動画 『第六ポンプ』パオロ・バチガルピが描く10個のディストピア
『第六ポンプ』パオロ・バチガルピが描く10個のディストピア 二週間で読み終えられるか?図書館で借りた2冊の本ー「空白を満たしなさい」「第六ポンプ」
二週間で読み終えられるか?図書館で借りた2冊の本ー「空白を満たしなさい」「第六ポンプ」 WordPress Popular Postsに黄色の警告文が表示される【解決】
WordPress Popular Postsに黄色の警告文が表示される【解決】 「Amazon重要なお知らせ:ご注文の詳細とキャンセルについて」という詐欺メールが来ました
「Amazon重要なお知らせ:ご注文の詳細とキャンセルについて」という詐欺メールが来ました